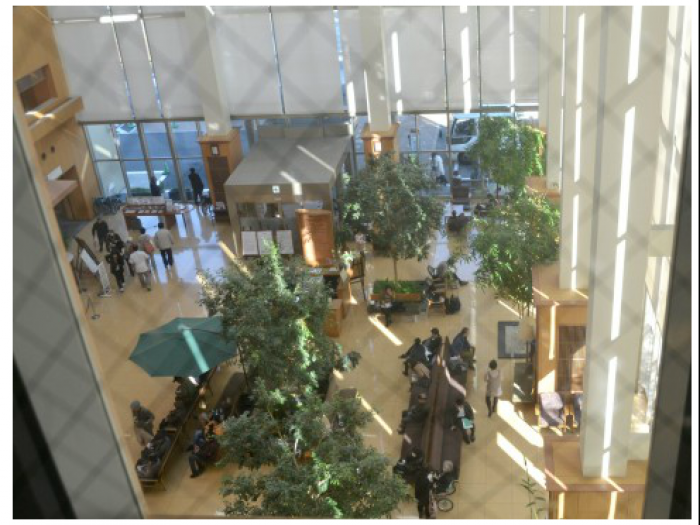- TOP
- >
- 1型糖尿病長期罹患者でも多くに内因性インスリン分泌能が残存か
2017年7月15日 13:00
食事の偏りや運動不足など、生活習慣のもたらす影響が強いとされる2型糖尿病に対し、1型糖尿病は自己免疫性の疾患とみられ、発症すると数年以内に自らのもつインスリン分泌能は失われてしまい、それゆえインスリンの自己注射などによる外部からの補充をずっと続けていかなければならないものと考えられてきました。
研究グループは、ウプサラ大学の病院で1型糖尿病を発症して10年以上が経過している18歳以上の患者113人を調査対象として集め、超高感度C-ペプチドELISAにより、残存した膵β細胞の機能について調べました。
また、血漿中のインターロイキン-35(IL-35)を含む循環サイトカインについて測定し、C-ペプチドが陽性だった患者14人と、陰性だった患者12人、比較対照群となる健常者の15人から血液サンプルをとって分析することも行っています。
そして、C-ペプチドが陰性であった患者では、サイトカインのIL-35の血中濃度が顕著に低く、それに付随する調節性T細胞や調節性B細胞、IL-35の産生に関わる細胞の比率における減少も有意に関連して生じていることが確認されたそうです。
一方、C-ペプチド陽性患者の場合はIL-35の血中濃度が高く、関連するその他細胞の比率減少との関連性はより低くなっていました。これまでの研究により、IL-35は免疫系で重要な働きを担い、調節性T細胞の表現型を維持するほか、Tヘルパー17細胞の分化を阻害、β細胞に対する免疫攻撃を弱める力をもつことが判明しています。
これらの結果から研究グループでは、発症から10年を超えた1型糖尿病患者などでも、膵β細胞の内因性(インスリン分泌)機能を残している人は少なくなく、残存がみられる患者とそうでない患者には、免疫学的な違いがみられること、とくにIL-35の産生が機能残存患者ではるかに高くなっていることが分かったとまとめました。
今回の知見は、残されたインスリン分泌能を活かしていく方法など、新たな治療法開発につながる可能性があります。
(画像は写真素材 足成より)

Diabetes Care : Increased Interleukin-35 Levels in Patients With Type 1 Diabetes With Remaining C-Peptide
http://care.diabetesjournals.org/
セミナー「スポーツ栄養のエビデンスを学ぼう!第76弾」を開催(2月7日) As-meエステール、マタニティ世代女性を対象に「栄養不足に対する意識」などを調査(2月5日) 「ヨメルバ」、「子どもの食事に関する調査」を実施(2月1日) 自然農法センター、「第5回オーガニック学校給食フォーラム」を開催(1月31日) NEXERが「管理栄養士・栄養士の印象と感謝エピソードに関する調査」を実施(1月10日)

わずかながらも内因性分泌能残存のケースは多数
しかしそうした定説を覆す最新の研究結果が報告され、注目を集めるところとなっています。その研究はDaniel Espes氏らのグループによるもので、彼らは1型糖尿病を発症して長期間が過ぎている患者でも、その多くで膵β細胞の機能が完全に失われているわけではなく、内因性のインスリン分泌能を保持していることが分かったと報告しています。同研究の論文は「Diabetes Care」オンライン版に6月15日付で掲載されました。研究グループは、ウプサラ大学の病院で1型糖尿病を発症して10年以上が経過している18歳以上の患者113人を調査対象として集め、超高感度C-ペプチドELISAにより、残存した膵β細胞の機能について調べました。
また、血漿中のインターロイキン-35(IL-35)を含む循環サイトカインについて測定し、C-ペプチドが陽性だった患者14人と、陰性だった患者12人、比較対照群となる健常者の15人から血液サンプルをとって分析することも行っています。
インスリン分泌能残存者ではIL-35の血中濃度が高め
その結果、1型糖尿病を発症してから10年以上と罹患期間が長くなっているにもかかわらず、わずかな内因性のインスリン分泌能は残っている患者が少なくないことが分かりました。そして、C-ペプチドが陰性であった患者では、サイトカインのIL-35の血中濃度が顕著に低く、それに付随する調節性T細胞や調節性B細胞、IL-35の産生に関わる細胞の比率における減少も有意に関連して生じていることが確認されたそうです。
一方、C-ペプチド陽性患者の場合はIL-35の血中濃度が高く、関連するその他細胞の比率減少との関連性はより低くなっていました。これまでの研究により、IL-35は免疫系で重要な働きを担い、調節性T細胞の表現型を維持するほか、Tヘルパー17細胞の分化を阻害、β細胞に対する免疫攻撃を弱める力をもつことが判明しています。
これらの結果から研究グループでは、発症から10年を超えた1型糖尿病患者などでも、膵β細胞の内因性(インスリン分泌)機能を残している人は少なくなく、残存がみられる患者とそうでない患者には、免疫学的な違いがみられること、とくにIL-35の産生が機能残存患者ではるかに高くなっていることが分かったとまとめました。
今回の知見は、残されたインスリン分泌能を活かしていく方法など、新たな治療法開発につながる可能性があります。
(画像は写真素材 足成より)
Diabetes Care : Increased Interleukin-35 Levels in Patients With Type 1 Diabetes With Remaining C-Peptide
http://care.diabetesjournals.org/
-->
リファイドニュース新着
記事検索
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ